空を映す水
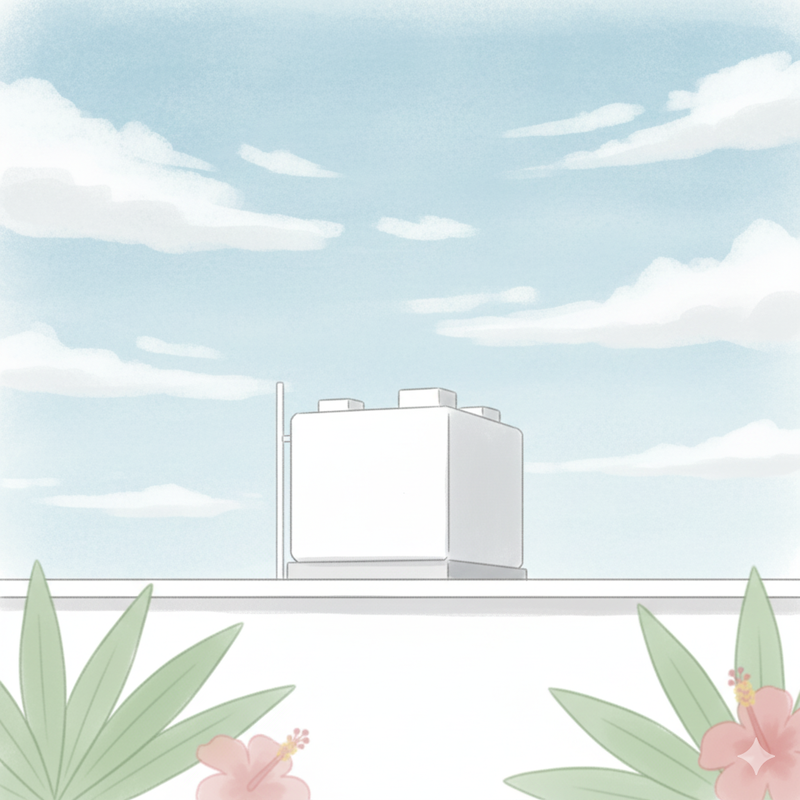
いつものように蛇口をひねり、手を差し出す。その瞬間、昨日までとは明らかに違う感触に、思考がふと止まった。
掌(てのひら)に当たったのは、あのまとわりつくような「生ぬるさ」ではない。かといって、本土で経験するような、身を刺す「冷たさ」とも違う。それは、強烈な日差しに焼かれ続けた肌を、ようやく鎮めてくれるような、清澄な「涼やかさ」だった。
ここ沖縄の水は、多くの場合、一度空へ一番近い場所へと登る。屋上に据えられた、あの白い水タンクの中へ。
長い夏の間、タンクは島を焦がす太陽に炙られ、その中の水は、蛇口をひねる前からすでに熱を帯びている。シャワーから出る湯のような水は、季節の停滞、逃れられない熱の象徴でもあった。
だが、今、私の手に触れているこの水は違う。
この涼やかさは、地面の奥深くからやってきたものではない。これは、空の気配そのものだ。ここ数日、島の空気を入れ替えるように吹き抜けていった、澄んだ北風(ミーニシ)。そして、夜ごと深まる秋の夜気(やき)が、屋上のタンクを静かに、しかし確実に冷やし続けてきた証なのだ。
タンクの水は、大地ではなく、この島の空の温度を映し出す鏡だ。
太陽の力が和らぎ、夜がその主導権を取り戻し始めたこと。空気が、熱を蓄えるものから、熱を奪うものへと静かに変質したこと。そのすべてを、この一筋の水が教えてくれる。
顔を洗う水が、火照りではなく、眠気を洗い流してくれる。この心地よい緊張感は、北国から届く「冬の便り」とは異なる、亜熱帯の「秋の目覚め」だ。
本土の人が、地中深くから上る水の冷たさに大地の律動を感じるとすれば、私たちは、屋上で空気にさらされた水の涼やかさに、空の移ろいと、ようやく訪れた休息の季節を感じる。
掌に溜まった水をすくい上げながら、私はこの島が、ようやく長い夏から解放され、深く息をついたのだと知るのである。